⭐️この記事のざっくりまとめ
・合計所得金額が45万円以下になると住民税が非課税になる。
・住民税非課税になると、国民健康保険料の減免などさまざまな優遇が受けられる場合がある。
見落としがちな支出(社保、税金)
普段会社員として生活していると税金や社会保険料は給料から自動で天引きされているため、これらの支払いについて普段あまり意識していない人も多いのではないでしょうか。セミリタイア(サイドFIRE)後は当然ながら諸々の税金と社会保険料は自分の貯蓄から支払わなければならないのですが、これが意外と盲点で生活設計で月々の支出に加えることを忘れていたりします。筆者は忘れてました。

ぼくにかかるお金は枝豆代とお水代だけなのだ。人間は大変なのだ

住民税や国民健康保険料や国民年金など行政への強制サブスクが毎月襲いかかってくるんですよね。

生きてるだけでお金が自動でかかるなんて人間は大変なのだ

ところが、一定の条件を満たすと住民税が非課税になり、さらにさまざまな優遇(ほぼ特典)を受けられる公的制度があるのです。

のだ!?
セミリタイア後に襲いかかってくる住民税

まず、住民税についてざっくりと。住民税は2つの方式で課税されています。
均等割 その自治体に住む人に対して定額に課税される。基本料金のようなもので、大体年間5,000円程度。
所得割 その人の前年の所得(所得=収入ー経費)に対して課税される。所得が高い人ほど住民税も高くなる。
年収ごとの住民税(所得割)で課せられる大体の金額は以下の通り。独身者で扶養なしの場合です。
| 年収(万円) | 所得割(万円) |
|---|---|
| 200 | 5.9 |
| 300 | 11.4 |
| 400 | 17.3 |
| 500 | 23.8 |
| 600 | 30.3 |

独身・扶養なし、年収400万円の人なら所得割は約17万円です。これに均等割の約5,000円を足したものが住民税の額になります。

年間17万5千円だから、ひと月あたり1万4,500円くらいなのだ。
住民税は前年の所得に対して課税されるものですから、セミリタイア後の最初の1年は給与収入がなくなったにも関わらず、この金額が無慈悲に襲いかかってきます。残念ながらこれを完全回避する方法はありません。

完全に回避はできませんが、ふるさと納税など住民税の控除を受けられる制度を使えばダメージを軽減することはできます。
住民税非課税になるには
所得が少ない場合など

住民税非課税になるには以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1.生活保護を受けている
2.障害者・未成年・寡婦(寡夫) で合計所得金額が135万円以下など
3.所得が少ない場合
会社員からセミリタイアすると、給与収入がなくなるため「3.所得が少ない場合」に当てはまる可能性が出てきます。
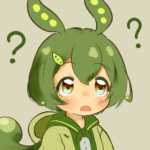
所得が少ないって具体的にいくらなのだ?

「所得が少ない場合」とは、地方税法にもとづき45万円以下と決められています。
ここでいう「所得」は、給与所得だけではなく副業などで得た事業所得や不動産所得なども含めた「合計所得金額」なので、副業など他の手段で稼いでいる人は非課税にならない可能性があることに注意。

単身・扶養なしの人で収入が給与だけの場合、年収110万円以下の人が非課税ラインとなります。
給与年収110万円 ー 給与所得控除65万円 = 所得金額45万円
(令和8年度)

お給料を110万円までに抑えれば住民税は0円になるってことなのだ。

住民税の所得割も、均等割の約5,000円も合わせて非課税になります。
ただし自治体により均等割は課税される場合もあるようなので注意です。
住民税非課税、さまざまな優遇

住民税が非課税になると数々の優遇を受けられます。
一例を以下に挙げていきますね。
国民健康保険料の減免
国民健康保険料は自治体により異なりますが、法律にもとづき最大で保険料の7割が減免されます。横浜市を例にすると、40歳単身者の場合、年間68,510円のところ、7割減により20,553円となります。

笑えるくらいお安くなってるのだ

7割減免を受けるには、合計所得金額が43万円以下の場合です。同じく合計所得金額により、5割減免または2割減免を受けられる場合があります。
高額療養費の自己負担金額が低くなる
高額療養費の自己負担金額は年齢と年収により異なりますが、「住民税非課税世帯」の区分を設けて低所得者への配慮がなされており、他区分よりも約22,200円〜217,000円以上も安いです。

協会けんぽによると、70歳未満で住民税非課税世帯の場合、自己負担金額の上限は35,400円となっています。
高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費より(協会けんぽのサイトに移動します)
国民年金保険料の免除や猶予が通りやすい
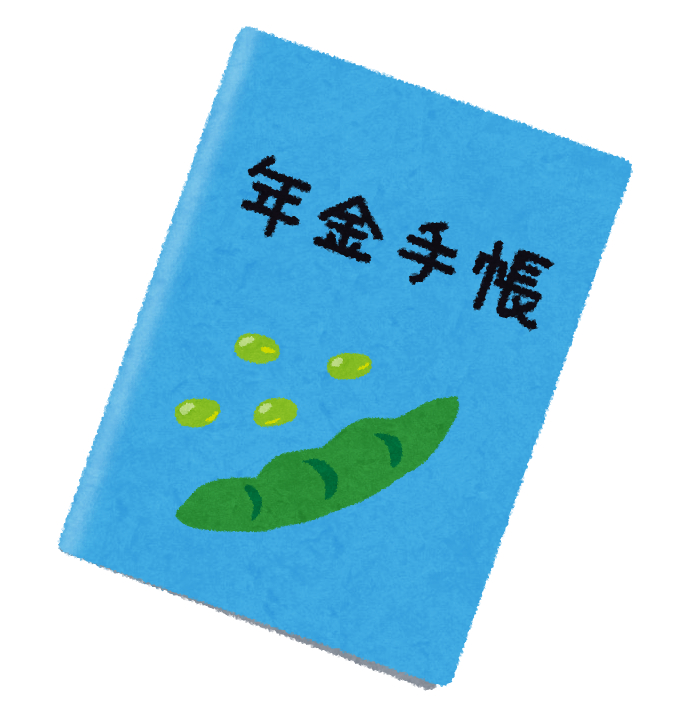
国民年金保険料は審査により、免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)または納付猶予を受けられる場合があります。審査は前年の所得をもとに判定されるため、住民税非課税の場合は必然的に認められやすくなります。単身・扶養なし者の全額免除の目安は所得金額67万円以下になっています。
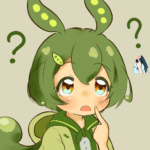
年金制度は将来の改悪間違いなしと言われるけど、それでも納めるのが無難って言う有識者も多いのだ。免除を受けるのは本当に良い手と言えるのだ?

免除を受けても将来の支給額が0にはならないのです。全額免除の場合、免除期間のうち「本来納付して受給できたはずの金額の半分」を受け取る権利が認められています。

納付してないのに半額もらえるのはもはやバグなのだ

とはいえ、制度が改悪されたとしてもやはり全額納付が望ましいと思います。免除を受けても後から追納できますので、キャッシュに余裕があれば納付した方がいいでしょうね。
公営住宅の入居審査に通過しやすい
公営住宅の入居審査は、原則として前年の所得金額を基準に行われるので、住民税非課税になる水準の低所得の場合は審査に通過しやすくなります。

前年の所得が基準になるということは、会社を辞めてすぐだと所得があることになるから、審査に通らないってことにならない?

原則はそうなのですが、退職などで現在の収入が急減した場合も審査の対象と認められています。離職票や退職証明書を提出しましょう。
公営住宅は家賃が低く抑えられていますので、固定費を大きく削減することができますね。住民税非課税だと家賃は最低水準になり、2万円台になるケースも多いようです。
以上の優遇は一例で、このほかにも住民税非課税になるとさまざまな恩恵がありセミリタイア勢にとっては非常に助かりますね。ただ、自動で適用されるものだけでなく申請が必要なものも多いので、しっかり調べて自分がその対象になるのかはよく確認しないといけませんね。これら制度の恩恵を加味した上でセミリタイア後の生活設計を立てていきたいと思います。

固定費はどんどん削減していくのだ!
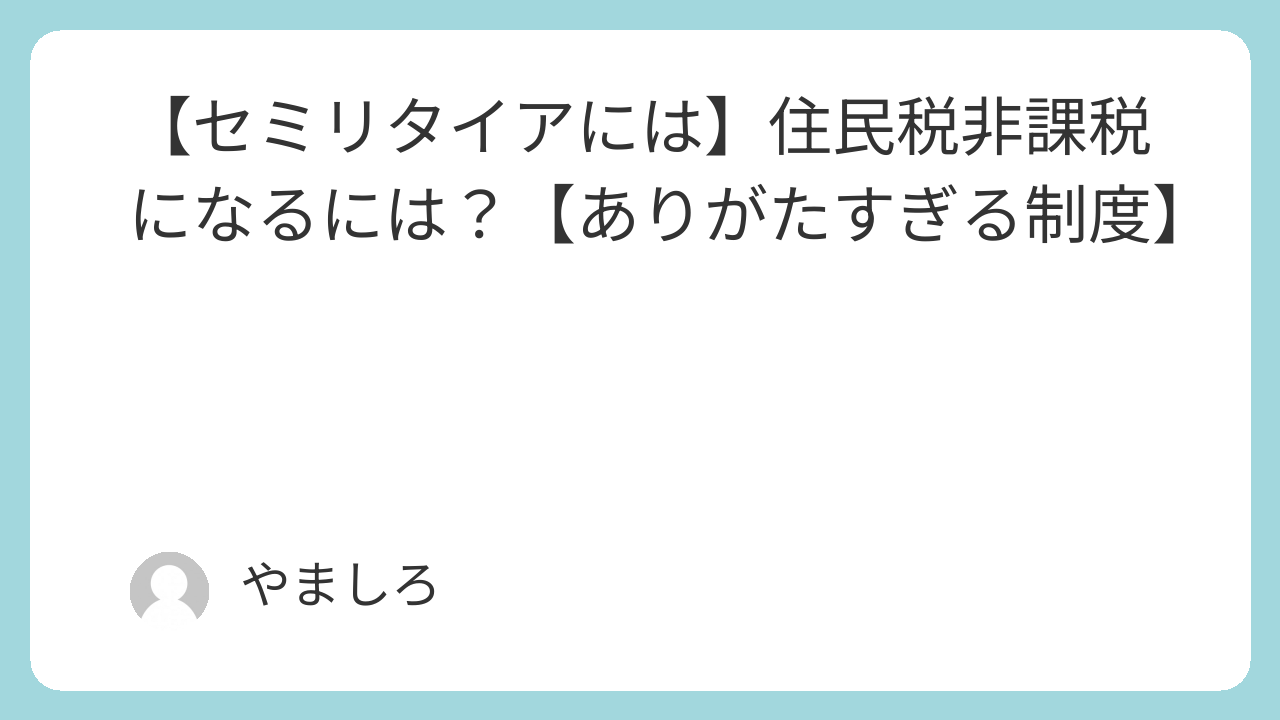
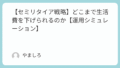
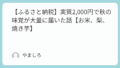
コメント